古き良きこと。過去から未来へつながること。
心が豊かになると自然に自分を癒す術が身についてきます。
日常に密着している日本の古き良き風習や習慣。
不思議な事。神秘な事。
あの世とこの世のつながりに関係している幸せになる術。
伝えていきたい風習や新しく生まれた習慣にオリジナリティな要素をプラスして綴っています。
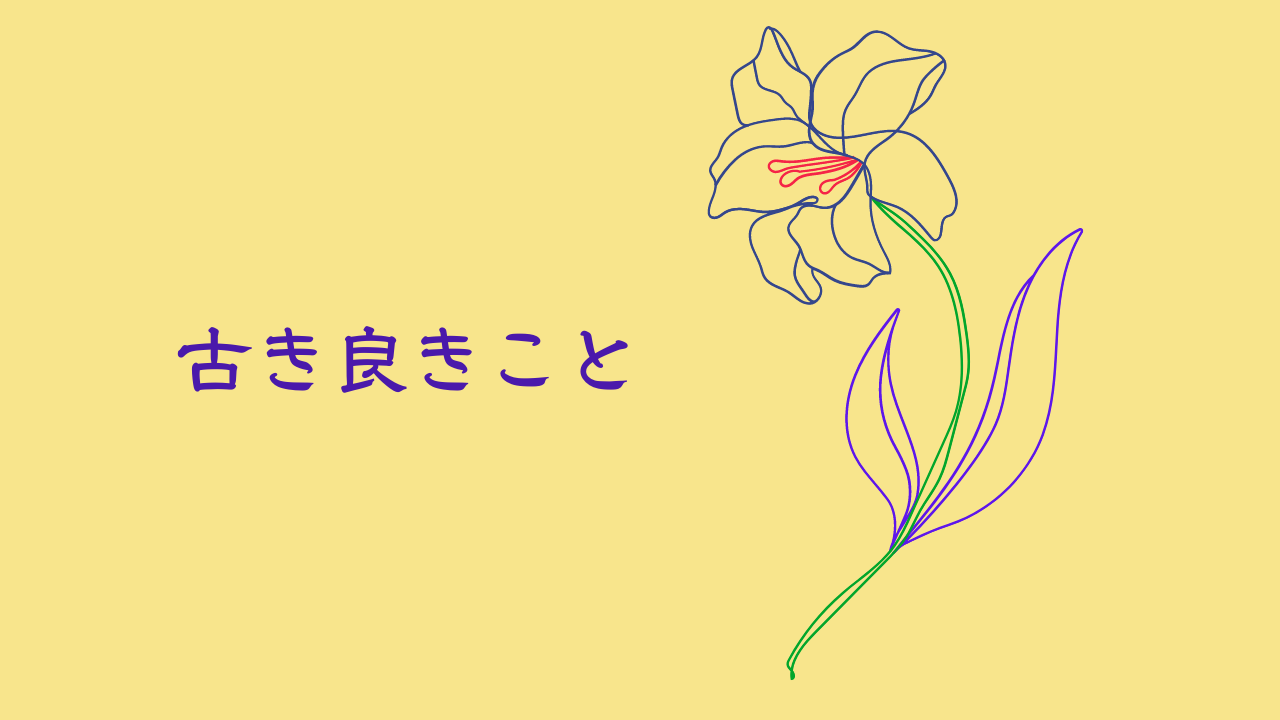 *古き良きこと
*古き良きこと 古き良きこと。過去から未来へつながること。
心が豊かになると自然に自分を癒す術が身についてきます。
日常に密着している日本の古き良き風習や習慣。
不思議な事。神秘な事。
あの世とこの世のつながりに関係している幸せになる術。
伝えていきたい風習や新しく生まれた習慣にオリジナリティな要素をプラスして綴っています。
 *日々の暮らし
*日々の暮らし  ⁑イベント & 祝日
⁑イベント & 祝日 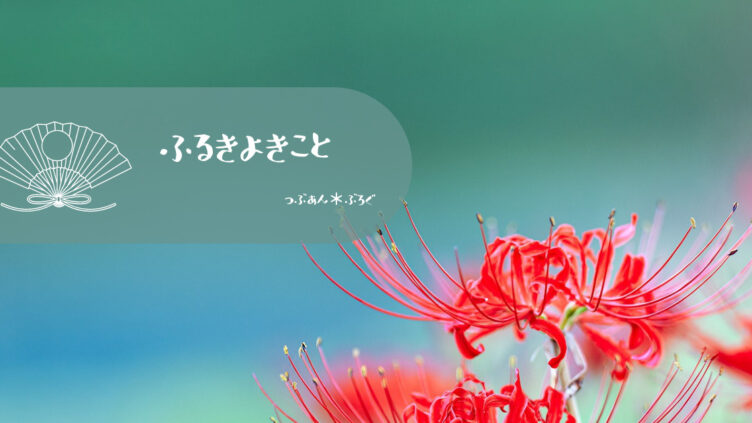 *古き良きこと
*古き良きこと  ⁑食
⁑食 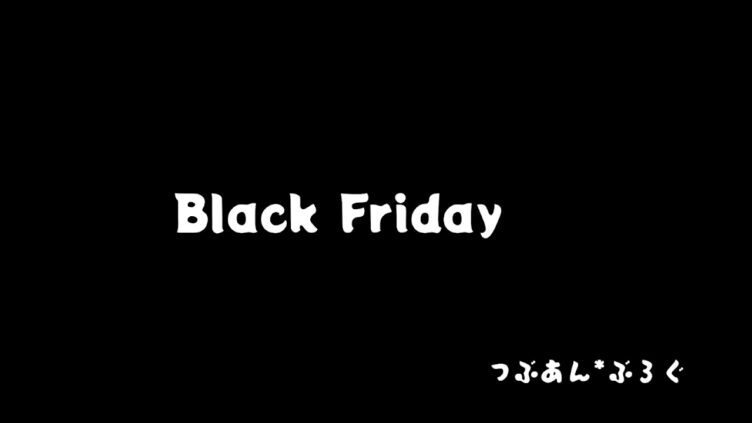 *日々の暮らし
*日々の暮らし  ⁑和風月名
⁑和風月名  ⁑和風月名
⁑和風月名  *古き良きこと
*古き良きこと 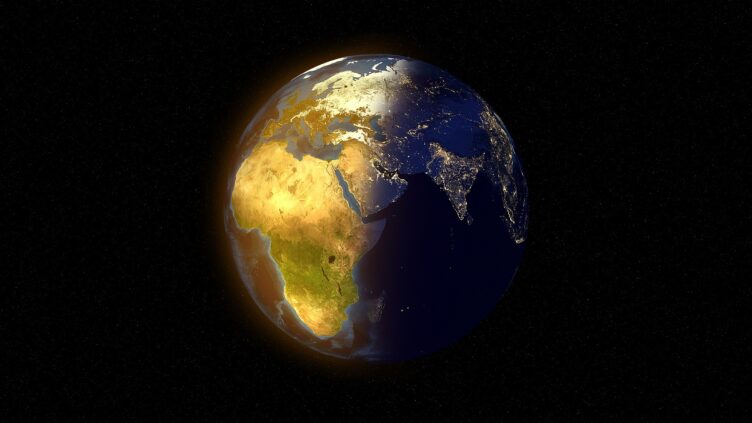 *古き良きこと
*古き良きこと  ⁑和風月名
⁑和風月名  *古き良きこと
*古き良きこと  ⁑和風月名
⁑和風月名  ⁑日本の神々
⁑日本の神々  ⁑和風月名
⁑和風月名  ⁑イベント & 祝日
⁑イベント & 祝日  *古き良きこと
*古き良きこと 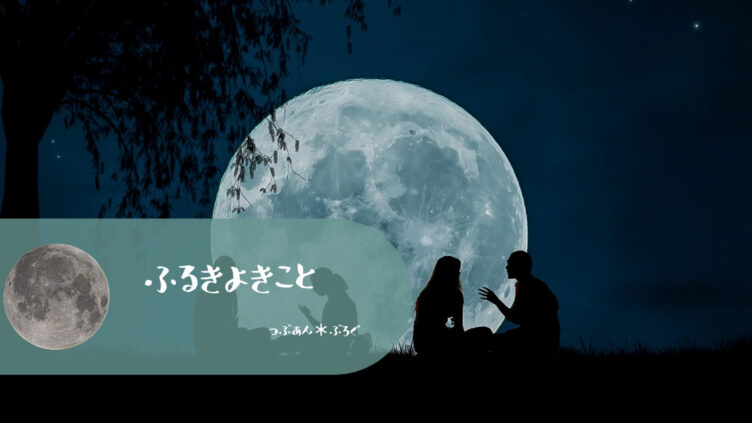 *古き良きこと
*古き良きこと  ⁑和風月名
⁑和風月名  ⁑和風月名
⁑和風月名  ⁑和風月名
⁑和風月名  ⁑和風月名
⁑和風月名  ⁑和風月名
⁑和風月名  ⁑和風月名
⁑和風月名  *古き良きこと
*古き良きこと  ⁑和風月名
⁑和風月名  *日々の暮らし
*日々の暮らし  *古き良きこと
*古き良きこと  ⁑和風月名
⁑和風月名  ⁑イベント & 祝日
⁑イベント & 祝日  *エッセイ
*エッセイ  ⁑日本の神々
⁑日本の神々  ⁑日本の神々
⁑日本の神々  ⁑日本の神々
⁑日本の神々  ⁑日本の神々
⁑日本の神々 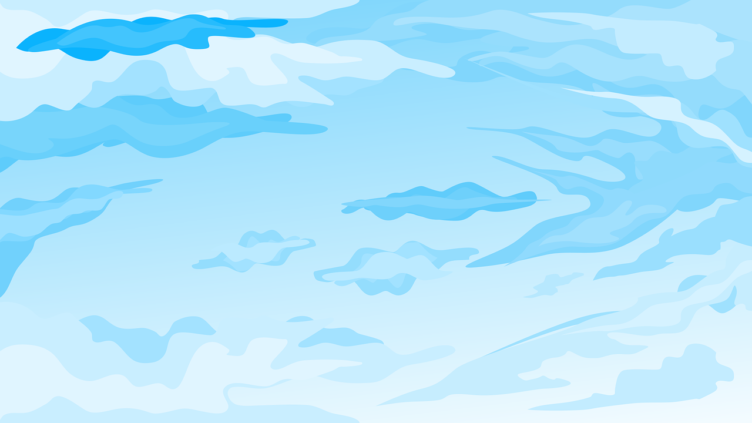 ⁑日本の神々
⁑日本の神々  ⁑イベント & 祝日
⁑イベント & 祝日  ⁑イベント & 祝日
⁑イベント & 祝日  ⁑日本の神々
⁑日本の神々 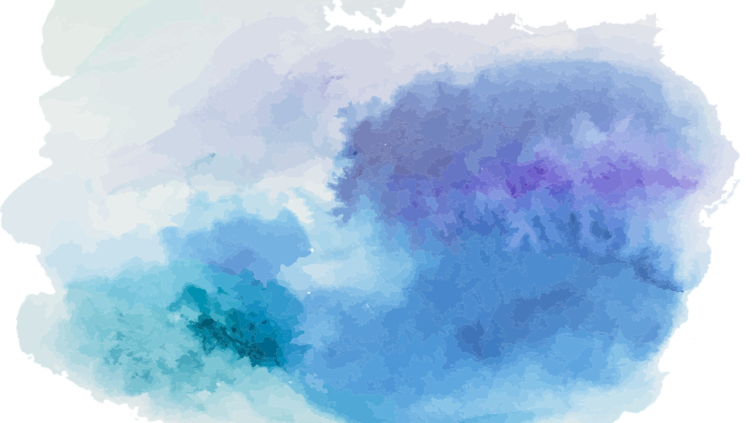 ⁑日本の神々
⁑日本の神々  *古き良きこと
*古き良きこと